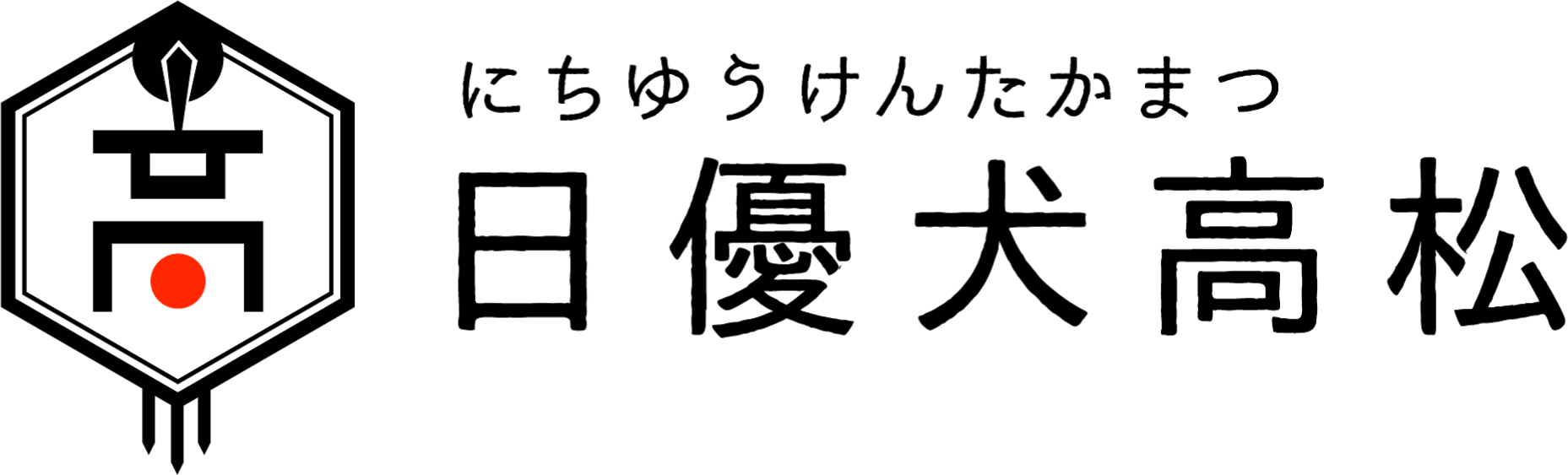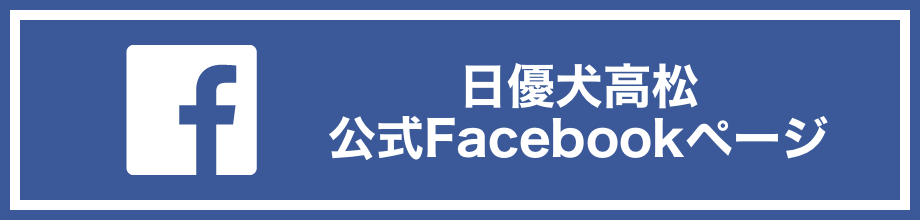療法食(りょうほうしょく)とは
ドッグフードの中で、療法食というフードを聞いたことがある方もおられると思います。愛犬が病気になり、病院で療法食を勧められたことがある方もおられると思います。
療法食は動物病院で販売している場合もありますし、ペットショップやホームセンターで販売されている場合もあります。
結論から言いますと、療法食で良いフードに私は出会ったことがありません。
病院で薦められた療法食の原材料を見れば、良いフードかどうかすぐに分かります。
実は、療法食には法律的な決まりは全くありません。
ペットフード安全法を管理している農林水産省のホームページに下記のようなQ&Aがあります。(一部を抜粋しています)
農林水産省のペットフード安全法のページより引用
Q.6 ペットフード安全法に特別療法食の定義はありますか。
A.6 ペットフード安全法上の定義はありません。Q.7 特別療法食の製造や輸入をするには、ペットフード安全法上どのような手続が必要ですか。
A.7 通常のペットフードの製造や輸入を行う場合と同様です。Q.8 特別療法食を販売するには、ペットフード安全法ではどのような手続が必要ですか。
A.8 通常のペットフードの販売を行う場合と同様です。Q.9 特別療法食と表示するにあたり、気をつける点はありますか。
A.9 上述のとおり、ペットフード安全法では、特別療法食の定義を定めていません。そのため、特別療法食の表示をする場合には、事業者の責任において、特別療法食と表示することが適切か判断する必要があります。
これらのQ&Aをご覧頂いてお分かりのように、療法食という法律的な決まりや定義すらないのが現状です。
カンタンに言えば、私どもで販売している国産ドッグフード「鶴亀長寿」も私が今日から療法食ですと言えば、療法食になります。
療法食とはそのようなものなのです。
療法食を食べると病気が改善するわけではない
療法食を作るときは、人工的に添加しているビタミンなどの量を調節して製造します。マグネシウムの量を減らしたり、ビタミンAの量を減らしてみたりして調整します。
しかし、いくら添加物のビタミンなどで調整しても、それ以外の原材料のもともと品質が悪いので、運よく症状が改善しても他のトラブルが多発します。
私どものところによく下記のように連絡をいただきます。
「病院の先生に言われて療法食に変えましたが、アレルギーがひどくなりました」
「療法食に変えてから、愛犬がドッグフードをいやいや食べていてかわいそうです」
「療法食に変えましたが、病気は全く改善しません」
「療法食を食べるようになってから、毛がパサパサになりました」
「療法食を食べるようになってから、愛犬が体を頻繁に掻くようになりました」
療法食は薬ではありません。薬のように実験して認可がおりたものでもありません。
もともとの原材料の品質が良くないドッグフードを、いくら人工的なミネラルなどを調整しても良いフードにはなりません。
療法食を販売しているドッグフードメーカーの戦略
病院で薦められる療法食のメーカーは、普通のドッグフードも販売しています。
業界的には、下記のように言われています。
自分のフードを食べて病気にさせて、病気になったワンちゃんに自分の療法食を食べさせるビジネスだと。
動物病院の先生は、ドッグフードのスペシャリストではありません。営業に来た大手海外産のドッグフードメーカーの営業マンの言うことを鵜呑みにしているだけです。
「本当に療法食を食べさせた方が愛犬にとってよいのか?」を飼い主様が大切な愛犬のために真剣に考えてください。